三保 浩一郎さん




広島東洋カープを愛する歯科医師です。
広島市で歯科医院をしていましたが、病のため歯科診療が出来なくなりました。しかし、歯科医として精力的に活動します。
人工呼吸器を着けていてもあちこちに行けるし、視線入力のパソコンでこのインタビューのように会話もできる。
もともと人を笑わせるのが好きだったから、それを貫いているだけ。実は発症直後は心が折れそうになった。
でも、すぐに立ち直った。娘にかっこ悪い姿は見せられんじゃん。
ALS協会広島県支部長の活動、歯科医師会の広報部の活動、バイク史の編集、野球観戦(カープ)…
やりたいことがあり過ぎるのが「玉にきず」
体は病に侵されようとも、心まで侵されないことが大切。
僕は自分の行動で世の中を変えたい。車いすに人工呼吸器でどんどん出掛けて、人々の意識を変えていきたい。

モトクロスレースに熱中していたころのわし。
この熱は冷めず、取材に取材を重ねた「広島オートバイレース全史」を編さん、出版することに!

カープと共に広島に育った、生まれながらのカープファン。
マツダスタジアムでのカープ観戦交流会。みんな笑顔じゃろ?

歯科医会の仕事に邁進・ワシの能力と知識を発揮できる場所はココじゃ!
![]()
気持ちの変化
![]()
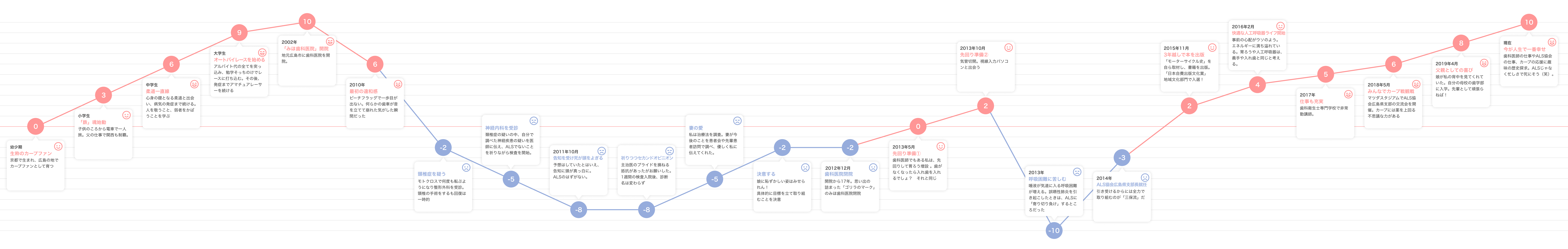

これは、2025年7月に三保浩一郎さんが佐賀県難病対策協議会で発表された内容を、抜粋しインタビュー風に読みやすくまとめたものです。(もちろん三保さんのOK済みです)
ALSと共に生きて15年。「ALS恐るるに足らず」と言い切る三保さんの言葉には、ユーモアと前向きな工夫がたっぷり詰まっています。
ちょっと笑えて、でも心に残る。そんな三保さんのお話をぜひ感じてみてください。
三保さん
こんにちは!三保浩一郎、広島市在住の58歳です。ALSを発症して15年、人工呼吸器を装着して9年になる歯科医師です。今は広島市歯科医師会広報部委員長やALS協会広島県支部支部長など、いろんな役職をしています。
ー発症から15年とのことですが、現在のお身体の状況はどうですか?
三保さん
眼球運動と一部の顔を除いて、指一本動かせませんし、しゃべることもできません。表情筋も動きにくいので、ちょっと面白いくらいでは笑顔になれないんです。初めて会う人はぶっきらぼうだと思うかもしれませんね。でも、それでも私はいろんなことができます。
ープレゼン資料のパワーポイントはアニメーションや合成読み上げ音声、動画など多くの演出がはいっていますが、それも三保さんがつくられたんですか?
三保さん
はい。視線でパソコンを操って制作したものです。「どんなソフトを使えば出来るの?」と気軽に聞いてくる人がいますが、地道に視線でパソコンを操作して作っています。僕の汗と努力の結晶です!
プレゼンの基本としては「まず、人を笑わせること」そこに重きを置いています(笑)。

ー今回のプレゼン資料をALSコネクトの皆さんにお見せできないのが残念ですが、なるべく伝わるように頑張りたいと思います。オヤジギャクも満載なのでそこもしっかりお伝えできればと思います(笑)
ー三保さんが最初に感じた症状はどんな感じでしたか?
三保さん
私の場合は脚が突っ張ってよくつまづくことでした。でも人によって違います。脚に力が入らない、箸を落とす、ろれつが回らないなど。特徴は運動をつかさどる神経だけに症状が出ることです。痛いのや痒いのはそのままなのに体が動かなくなる。蚊が止まって血を吸っているのが分かるのに、払いのけられない感じです。原因が分からないということは、あなたやあなたの大切な人が発症するかもしれないということなのです。
私が病名をALS(筋萎縮性側索硬化症)と告げると、かなりの確率で「あぁ、亡くなったホーキンス博士と同じ病気?」と言われます。
でも間違えないでください。ホーキン“ス”は靴のメーカー、有名な宇宙物理学者はホーキン“グ〜”博士です。(笑)
ー三保さん作成のスライドでは懐かしのエド・はるみさんの写真とともにホーキン“グ〜”がアニメーションとともに強調されていますね、これで確実に覚えました(笑)
ー発症前はどんな生活を送られていましたか?
三保さん
体力には自信があって、大学生で始めたモトクロスは20年レースに出ていました。柔道も中学から発症直前まで続けていました。同時にかなりの食いしん坊で、体重80kg以上、40年の“デブ歴”でした(笑)。でも発病後は筋肉量と一緒に体重も減って、今は50kg程度。もう“デブ”とは言わせません!(キッパリ)
ー現在は主にどのようなコミュニケーション方法を取っていますか?
三保さん
ALS患者は舌の動きが悪くなることで構音障害が出て、さらに気管切開して人工呼吸器をつけると、声はまったく出なくなります。声を失った多くの方が手話や筆談を使いますが、ALS患者は上肢も動かないことが多いので、それも難しいんです。
一方で、視力は奪われること無く、眼球の動きは最後まで残りやすいと言われています。だから「透明文字盤」で一文字ずつ伝えたり、今は私が使っている「視線入力パソコン」が大活躍しています。車椅子にも「視線入力パソコン」をつけて、カープ観戦に旅行にとあちこち出かけています。
余談ですが、4年前の私の誕生日には、家族から三密を避けたサプライズのプレゼントがありました。
ビルの下には見慣れぬ高級外車。「誰のじゃろうか?」と思った矢先に、「乗り込めと」・・・・・えっ?買ったんかい?!
座席の足元に人工呼吸器、吸引器を積み込んでオープンエアモータリング! 平清盛が扇で太陽を扇いだことで有名な音戸の瀬戸にGO!!! 以上、レンタカーでした・・・。


ー素敵なサプライズですね!逆にコミュニケーションが難しいなと思うことはありますか。
三保さん
私が最も腹立たしいのは、しゃべれないことで知恵まで遅れていると思われるような扱いをされることです。入院先の病院で看護師に、耳元で「みほさ〜ん、わかりますかぁ〜?」と鼓膜がむず痒くなるくらい大声で話しかけられたり…。かろうじて声が出る時期に出会った司法書士に「理解できますか?」と念押しされて、渾身の力で答えても信じてもらえなかったり。家族が「病気なんです」「話の内容は理解できています」とフォローしても無駄だったようで、しまいには「この方はどの程度理解できるのですか?」なんて言われました。
「オッサン、⾺⿅にするのもええ加減にせえよ! 半年前まで毎⽇歯科医師として診療しよったんじゃ。今は思うように声が出んだけじゃ。今すぐ出ていけ!」と言いたかったけど飲み込みました(笑)。代わりに「徳田虎雄※と同じ病気だ!」って言ったんです。妻が通訳してくれましたけど、それでも納得してなかったですからね。※徳⽥⻁雄さん(1938〜2024)徳洲会病院を設⽴した医師で衆議院議員だった元ALS患者
私の所には訪問看護師、訪問リハビリなど多くの医療職者が出入りしていますが、中には「口文字」や「透明文字盤」を使ってのコミニケーションを取ろうともしない方が見受けられます。意図的に忙しそうにして、私と目を合わせないようにしているんです。
一方で、私が信頼を寄せるスタッフは、何をする時でも時々目を合わせて、アイコンタクトや「口文字」でコミュニケーションを図りながら処置をしてくれます。
いずれにせよ、コミュニケーション方法の確保は非常に大切です。誤嚥性肺炎を起こした際も正確な病状や私の気持ちを伝えるのに大活躍しました。ひょっとすると、これらがなかったら死んでいたかもしれません。
ー誤嚥性肺炎になってしまった時のお話を聞かせてください。
三保さん
「歯科医なのに誤嚥性肺炎!」って自分でも思いました(笑)。11年前、気管切開はしていましたが、人工呼吸器はまだつけていない時期でした。昼に歯科衛生士から口腔ケアと歯石除去を受けて、その直後から咳が止まらなくなって…。翌朝には40℃の熱が出て、息苦しくて、パルスオキシメーターも80%台前半。脈も110。肩で息をするほどで、夜は「ワシもこれまでか…」と覚悟しました。
翌朝には⻭医者には馴染み深い“ドブ”のような嫌気性菌の悪臭を感じて、痰も白濁して悪臭を放っていました。感染性の肺炎を⾃覚した私は、訪問医に抗生剤の点滴をお願いして、すぐ効いてくれました。こうして人生で最恐怖の二日は終わったんです。

誤嚥性肺炎になってしまった原因は、実は「唾液」なんです。口腔ケアで歯石やプラークを含んだ不潔な唾液が気管に落ち込んだんです。誤嚥性肺炎というと食べ物を飲み込むときに誤って気管に入ると思われがちですが、主な原因は唾液なんですよ。
当時はなんとなく座位で受けていて、術者が見やすいようにやや上を向いていたんです。その姿勢が誤嚥を招きました。この件以降はベッド上で口腔ケアを受けるようにしています。さらに、唾液の誤嚥を防ぐために、歯科用フレキシブル排唾管をくわえて常に低圧で吸引しています。今の私は経口摂取できないので虫歯にはなりません。でも口腔が不潔だと唾液が耳に流れて中耳炎を起こすこともある。人工呼吸器を装着しても口腔ケアは大切なんです。
私はL8020乳酸菌入りのマウスウォッシュを使っています。⻭磨きを全くしておらず、汚れ放題なのに、⾍⻭も⻭周病も経験しない⼈を診ることが稀にあります。そういった人の口腔から見つかった乳酸菌で、善玉菌を増やして悪玉菌をやっつけようという発想が斬新なんです。開発者は広島大学歯学部の二川浩樹教授。私の大学院時代の先輩で、エロエロと世話になりました(笑)
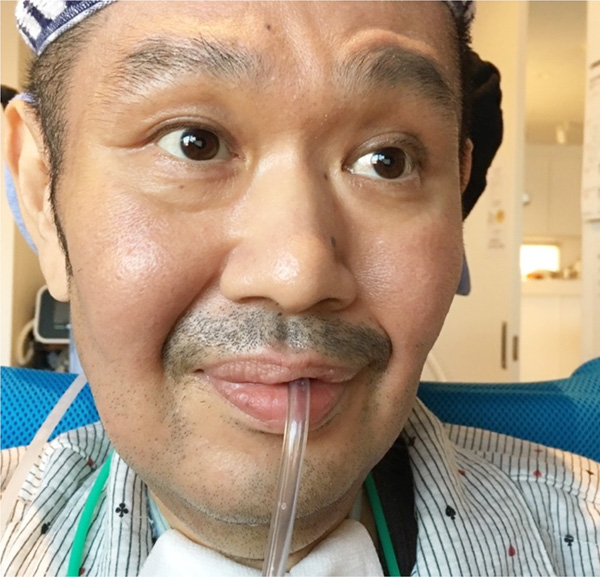

ー歯科医師ならではの詳しいお話ありがとうございます。大学院時代のお話は今度詳しくお聞かせください(笑)
続いて三保さんの訪問介護について教えていただけますか。
三保さん
人工呼吸器を装着すると、24時間必ず誰かにそばにいてもらう必要があります。着替えから排泄まで、私は全介助です。そこで介護保険に加えて「重度訪問介護」を利用して、ヘルパーさんに介護をお願いしています。重度訪問介護制度についてはケアマネと一緒に勉強してきました。ですが、痰の吸引まで引き受けてくれる事業所は少なくて…。そこで妻が管理者となって介護事業所を立ち上げました。現在は3人の人工呼吸器をつけたALS患者さんの介護を担っています。
ー介護事業所の運営だけでなく、本業の歯科医師としてのお仕事も続けていらっしゃるんですよね?
三保さん
広島市歯科医師会では広報部委員長や会史編纂特別委員会の委員長を任されています。会報誌の編集、広報用動画の編集、歯科医師会の歴史を後世に伝える仕事など、多くの役割を担当しています。
他の歯科医と一緒に仕事をするのは何より楽しく、生きがいになっています。身体が動かない私に仕事を任せてくれた広島市歯科医師会には、本当に恩義を感じています。「病人だから出来ない」と思われないように、全力で取り組むんです。
歯科診療が出来なくなった日には絶望しました。でも人工呼吸器を装着して生活が落ち着くと、無性に仕事がしたくなって…。歯科医師会に「診療がない分、他の先生より時間があるので仕事をさせてくれ」と掛け合ったんです。今では容赦なく(笑)、歯科医としての仕事をさせてもらっています。
仕事があること、社会の中で自分のポジションがあること、生きがいがあることは、とても大切だと考えています。
広島県歯科医師会の月刊会報誌には「ALS恐るるに足らず〜歯科医の綴るALS考〜」と題した連載を執筆していて、もう80回になります。県内の先生方から「ALS患者を訪問診療しているが役立っている」「患者と一緒に読んでいる」「診療方針の参考になる」といったメールをいただき、とても励みになっています。
私の本業はALS患者ではありません。今も、これからも歯科医です。
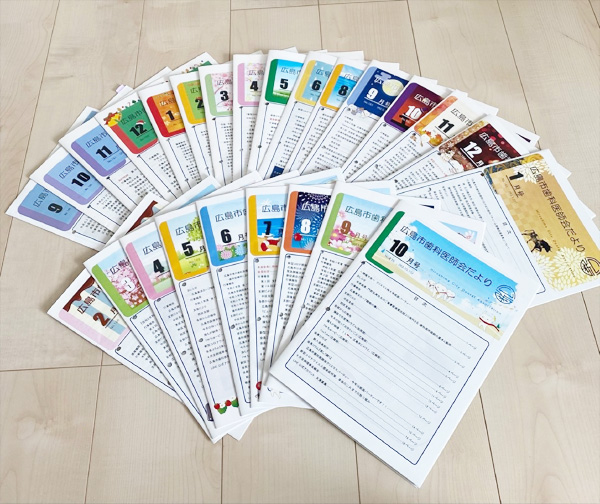
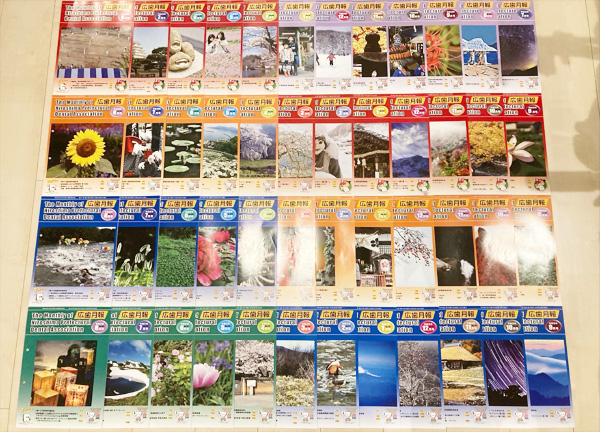
ーさらにALS協会広島県支部の支部長としても活動されていますよね。
三保さん
ALS協会の患者相談会では、「延命措置は受けたくない」「胃瘻も呼吸器もしたくない」と話される方が少なくありません。もちろん個人の考えは尊重すべきです。でも私はいつも心の中でこう思うんです。「俺を見てみろ。これは延命措置なんかじゃないぞ。絶対に」と。
私自身、病名を告げられた直後に主治医から人工呼吸器を装着するかどうかを迫られました。深く考える間もなく「装着します」と答えましたが、妻が率先して情報を集め、「呼吸器をつければALSで死ぬことはないんだって!」と背中を押してくれたことが大きかったと思います。
ALSによって家庭が崩壊する話も耳にしますが、うちの場合は「共通の敵」ができたおかげで、かえって家族の絆が強まったように感じています。ALSもまんざらじゃありません(笑)。
ただ、病名を告げられてすぐの頃は、正直「苦しまずに死ぬこと」や「人工呼吸器を装着しないこと」を考えていました。事故や災害のニュースで「死者が何人」と耳にするたび、「ワシが代わってあげたのに…」と感じたこともあります。
けれど実際に人工呼吸器を装着してみると、ガラリと考え方が変わったんです。装着以降を“第二の人生”ととらえ、精一杯生きる。それが今の私の選んだ道です。
ー“第二の人生”をより良く過ごすために、どんな工夫をされているのか教えていただけますか?
三保さん
在宅で暮らすためには医師、⻭科医師、看護師、リハビリ、介護⼠など、それぞれ異なる経験と知識を持った多くの医療職者・介護職者が関わります。
⾃分の⾝体は⾃分が⼀番分かりますから、⽅針は⼈任せにせずに⾃分で考え、決めて、医療職者の知識と技術を引き出すのがコツと感じています。
「船頭多くして船⼭に上る」と⾔いますが、船頭は患者⾃⾝であるべきと考えます。船頭の決めた針路をよく理解して、船頭の掛け声に合わせて櫓を漕ぐと船はグングン進みます!
多くの⽅から「病気に負けず、前向きで凄いですね」との⾔葉を頂戴しますが、当の本⼈に⾔わせれば微妙にニュアンスが違うように感じています。
私はこの病気、あらがってみたところで⻭が⽴つような相⼿ではないことに早くに気が付き、病気を受け⼊れ、⻑く付き合うことにし、その中で⾃⼰の出来るベストを尽くすように努めているだけと、感じています。
⼈間、無いものねだりしてもキリがありませんからね。肝⼼なのは努⼒です!
ALSという原因不明の病は、進行に伴って次から次へと身体の機能を奪っていきます。
そんな様子を見て多くの方が同情するのですが、歩けない脚の代わりには車椅子、摂食嚥下できない口の代わりには胃瘻、動かぬ手の代わりには視線入力パソコン、肺の代わりには人工呼吸器。
病状の進行に従って、失った機能を補うツールが増えていくだけのことです。
一つ一つは義足や義手、歯がない人の入れ歯、そして薄毛の人のカツラと同じです(笑)。
ーここまでのお話だけでも、三保さんがどのようにしてALSと付き合ってこられたかがよく伝わってきました。最後に、ALSと生きるうえで心に留めていることを伺えますか?
三保さん
私がALSと対峙する上で気を付けているのは、
・敵(ALS)をよく知ること
・知ることで事前の準備と対策ができるので、怠らないこと
・「あれも出来ない、これも出来ない」ではなく、「あれも出来る、これも出来る」というスタンスでいること
・社会との接点、友達や仲間との付き合いを絶やさないこと
・苦しい時でもユーモアを忘れないこと
こうしたことを守ってきたからこそ、「ALS恐るるに足らず」と言えるようになりました。
ALSと暮らすのは楽ではありません。
健常者の生活を「東京まで新幹線で行く」と例えるなら、ALSの暮らしは「徒歩で東京へ行く」ようなもの。疲れるし、時間もかかります。
でも、考え方を変えれば徒歩の旅も悪くありません。見える景色は違うし、土地ごとの食事も楽しめる。何より、到達したときの達成感は格別なはずです。私はそんな気持ちで「ALS道中膝栗毛」を旅しています。
ALSは奪うばかりではありません。新たな出会いもあり、体が動かなくなったからこそ学べたこともたくさんあります。
ALSによって失ったものを10とするなら、得たものは6くらいだと感じています。けれど、生き方次第でその6を8に、10に、15に増やしていける――私はそう信じています。
ーALSと向き合う中で見えてくる景色も、得られるものも、人それぞれかもしれません。けれど三保さんが実際に続けてきた努力、生み出した工夫、そして心がけがあるからこそ、「ALS恐るるに足らず」と今、はっきり言えるのだと感じました。その言葉はALSとともに生きる仲間の方々にとって大きな支えになると思います。
ありがとうございました!また色々とお聞かせください。
開く
![]()
病名を告げられた直後に主治医から人工呼吸器を装着するかどうかを迫られました。深く考える間もなく「装着します」と答えましたが、妻が率先して情報を集め、「呼吸器をつければALSで死ぬことはないんだって!」と背中を押してくれたことが大きかったと思います。
ALSによって家庭が崩壊する話も耳にしますが、うちの場合は「共通の敵」ができたおかげで、かえって家族の絆が強まったように感じています。ALSもまんざらじゃありません(笑)。
ただ、病名を告げられてすぐの頃は、正直「苦しまずに死ぬこと」や「人工呼吸器を装着しないこと」を考えていました。事故や災害のニュースで「死者が何人」と耳にするたび、「ワシが代わってあげたのに…」と感じたこともあります。
けれど実際に人工呼吸器を装着してみると、ガラリと考え方が変わったんです。装着以降を“第二の人生”ととらえ、精一杯生きる。それが今の私の選んだ道です。
じっとしていられない性分の私は遠征することも多いのですが、この時の困りごとの一つがホテルの部屋探しです。車いすで入っていけるか?コンセントは使いやすい場所にあるか?
事前にホテルに問い合わせ、見取り図があるなら確認し。そうして入念に下調べをしていっても、現地についてみると「あれ、車いすが引っかかって通れんじゃん」ってこともままあります。東横インのハートフルツインTypeBなど、全国で部屋の規格が統一されていると助かるのですが、そんなホテルは稀。部屋探しは主に妻がやってくれていますが、妻の負担を軽くしてもらえんじゃろか。
彷徨える歯科医
三保 浩一郎さんのFacebook
三保 浩一郎さんのYoutube
日本ALS協会広島県支部HP