柴田 薫さん




子どものころからプラモデルなどモノづくりが大好きで、2023年3月に病気の関係で退職するまでは、自動車会社の生産技術の研究職で、産業用ロボット動作の自動化技術の研究や、溶接の非破壊検査技術の研究などを行っていました。
インドアと思いきや、1200ccの大型バイクを社会人になっても乗り続けています。大学生のときはバイクに無線機つけて、そのスイッチをブレーキのところにつけて、ヘルメットにマイクとスピーカー仕込んで、先輩と一緒にツーリングなんていう発明?もしたりしてました。
体が動かなくなっても、自分は自分。モノづくり好きは変わらないです。今も生活をより快適にするために、世の中にある様々なものを組み合わせ工夫して、趣味と実益を兼ねて楽しんでいます。工夫の様子を載せているのでぜひ見てください。

発症前まではバイクツーリングが趣味で、ソロでのワインディングロード走行などを楽しんでいました。

旅行や食べ歩きも好きで、家族と温泉によく出かけていました。現在も、車椅子で家族とバリアフリーの温泉に1泊旅行に行ったりしています。

友人達とスポーツ観戦などにも車椅子で出かけています
![]()
気持ちの変化
![]()
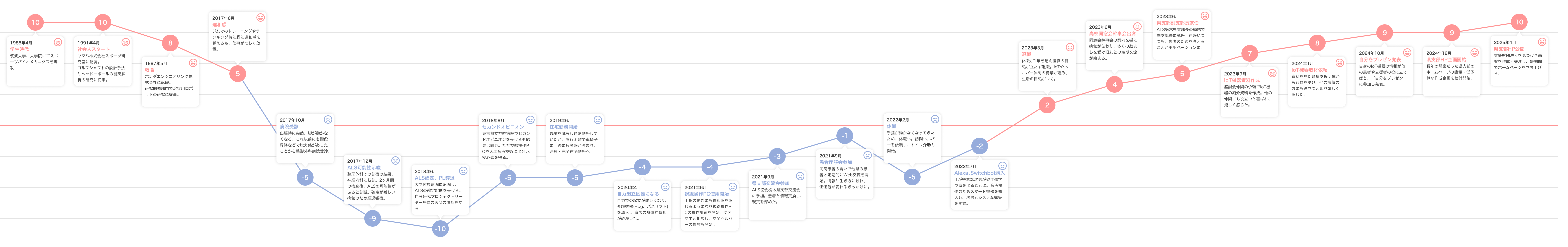
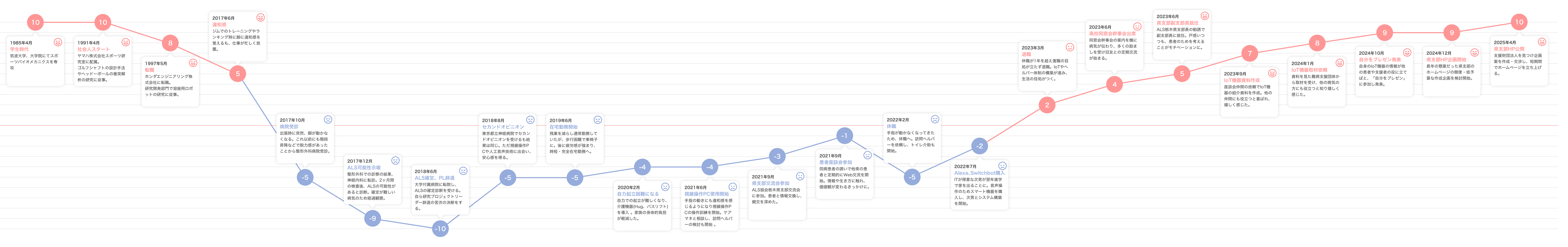
2時間近くたっぷりとお話しをお伺いしました。常に笑顔で、様々な工夫されたツールをお見せいただき、時には奥様も参加してくださり、楽しい時間を過ごさせていただきました。
そんな柴田さんのお話をたっぷりお届けします。
ーIoTの活用を考えるようになったきっかけは何ですか?
柴田さん
病気がわかったのは2017年の年末で、ALSの告知を受けたのは2018年の夏でした。場所は栃木県下野市にあるJ病院です。
そのあとセカンドオピニオンで、T病院に1ヶ月間、検査入院しました。
そこで出会ったのが、作業療法士のH先生です。
H先生は、今ある機能を活かしていろんなことができないか、という視点でいろいろな取り組みをされている方でした。
その中で、視線でパソコンを操作できる「HeartyAi」、テキストを音声に変えるソフト、自分の声を録音して合成音声を作る「Myvoice」などを使っていました。
あるときH先生から、「柴田さん、今後どう進行するかわからないけど、検査入院で1ヶ月あるし、声とか残してみませんか?」と声をかけられて、病院内の録音室で録音をすることになりました。
期間はだいたい1週間くらいだったと思います。
H先生がパソコンを操作しながら、ひとりでいろいろ作業しているのを見て、「大変そうだな」と思って。
「私、パソコンできますよ。やりますよ」って声をかけて、自分で操作しながら録音データの編集を行いました。
そのときに視線操作の方法も教えてもらって、データやソフトも一式いただいてきました。
手が動かなくなったとき、声が出なくなったとき──
そういうときに、こういう方法があるんだということを、このとき初めて知りました。
ー検査入院のときにH先生から「将来動けなくなったり声をだせなくなったりする」と聞いた時どういう気持でしたか?すんなり受け入れられましたか?それともやっぱりすごく戸惑って躊躇したりとか
柴田さん
私は逆にこれがあれば手が動かなくなっても大丈夫だなと安心しました。それまでは何もできなくなるのではと思っていましたが、パソコンでつながることができれば、エクセルもパワポもLINEメールもできる。これならと希望に感じました。何ができなくなるというというより「いざ」っていうとき、こういうことができるということを知ることで全然気持ちは変わります。
病気になって告知をうけるまでの間ですが、最初は栃木の神経内科にかかりはじめたのが2017年11月。ALSかもって言われたのはその1ヶ月後の2017年12月。結局診断がつかずに2018年の5月まで待って、それでも診断がつかなくてJ病院に行ってくれと言われました。その間に「もうALSだろう」と、どうやって進行するのかなど調べました。
そうなったときにどうしようって色々と頭に浮かびました。その対処法をH先生に聞けたことで色々できるとわかって、気持ちとしてだいぶ変わりました。
ーなんで自分が・・という気持ちに囚われたり、ふんぎりがつかず苦しむんじゃないかと想像しましたが
柴田さん
H先生に会うまでの期間は、ある意味すごく大きかったですよ。
高校の友人に精神科医がいるので、その友人と話して、ALSという病気がどういうふうに進んでいくかについては、ある程度わかっていました。
でも、ばらつきのある病気だし、そこにとらわれすぎてはいけないなとも思ったんです。
それと、やっぱり家族ですね。子どもが3人いて、当時は長男が大学生、次男が高校生、娘はまだ中学生でした。
子どもたちのことをなんとかしないといけない、っていうのが一番にありました。
最初はすごく落ち込んだけど、妻が明るい性格で、妻に助けられたのも大きかったですね。
だから、そこはある程度、気持ちを切り替えていくことができました。
自分はもともとロジカルな人間というのもあって、「決まったものはしょうがない」と思えるところもありました。
そのときは、自分の生活の心配よりも、子どもたちのためにお金をどうしようとか、自分の仕事のプロジェクトをどうしようとか、そっちのほうが心配でした。
でも、自分の身体が動かなくなったときに、その代わりになるものや技術があると知って、希望になりました。
もともとそういう仕事をしていたこともあって、それらの技術がどのくらいのことができそうかっていうイメージは、ある程度持てていました。
パソコンをベースにすれば、ある程度のことはできそうだなって。
ALSの大家といわれる先生の話を、何かの本で読んだんですけど――
【ALSになった人たちは薬を求めて、治療法を求めて、いろんなことをやってる。今の段階では残念ながら治療法はない。だからこそ、残された時間を“自分らしく生きること”に使っ
たほうがいいと私は思う】
これは、ある患者さんに向けて言った言葉らしいんですが、「なるほどー」って思いました。
自分は薬の開発者じゃないので、そこは任せるしかないし、ただ待つしかない。
でも、ただ待ってるだけだと人生終わっちゃう。
だから、自分にできる別のことを考えて、やってみようと思った――そんな感じですね。
ーもともとロボットの研究をされてきた柴田さんとして、そこに一つのテーマを投げかけられたというような感じでしょうか
柴田さん
ロボットをやってた私からいうと、人の体をロボットで扱うのは非常に難しいです。安全性を含めて作業ロボットとかまだ現実的ではない。それで言うと、物理的に何かするものよりは、ロボットみたいなフレキシブルなアームはないけれど、「Hug(ハグ)」っていう機器がありますが、足が立たなくてもそこに抱きついて上げてもらってトイレに行くいこともできるんです。これも「移乗サポートロボット」って呼ばれてますけど。
ーロボットと「協力し合いながら」ということですね
柴田さん
そうですね。助けてくれるロボットです。車椅子もちょっと特殊なんですけど、姿勢を大きく変えることができます。フルフラットにも立ち上がることもできるんです。ペルモビールという名前です。ジョイスティックで色々動かせるんですが、今私はジョイスティックも動かせないので動かせる4本の指のところにボタンをつけてそれで車椅子を動かせるように改造してもらってます。ボタンも今の指の力で押せる強さでの調整なども入っています。後ろにもコントローラーつけてもらって介護者モード自分で動くモードなどの切り替えもできるようになってます。

ーすごい進化ですね
柴田さん
スウェーデンの会社の車椅子で、日本にはあまり入っていないかもしれません。
でも、アメリカではALS患者の8割くらいがこの車椅子を使ってるそうです。クッションもすごく良くて。
車椅子で座ってて何が辛いかって、おしりの痛さなんですよね。よく褥瘡になったりする人もいますし。
一回痛くなると、4〜5日は痛みが続きます。姿勢を変えることで、体にかかる圧を分散することができるんです。
今、1泊くらいの旅行ならできるんですけど、そのときもこの車椅子に乗ってます。車に積んでいく感じです。
立ち上がれる機能は、圧を分散できるって意味でもいいですし、ALS患者は足に荷重をかけることは良いってALSの先生もおっしゃってます。私はあんまりやってないですけどね(笑)
ー柴田さんなりの現状に合わせて、いろんなものでサポートしあって今までの機能で実現するという感じなんですかね?
柴田さん
そうですね。今あるものの中から、自分に合ったものにどんどん変えていくって感じです。
パソコンも、OSがバージョンアップされるたびに、センサーに不具合が出ないかとか、確認しないといけない。
視線入力のパソコンって、普通に買うと50〜100万くらいするので、自費だと大変なんですよね。
生活補助具として申請すれば割引で買えるんですけど、自治体によっては申請が通るまでに時間がかかる。
この病気は、進行が早い人は本当に早いから、届いた頃にはもう使えなくなってる、なんてこともあります。
今、自分が使ってるセンサーは3万円くらいのもので、もともとはゲーム用の視線入力にも使われてるもの。
量産されてきてるから、価格もかなり安くなってきています。ソフトは無料だし、センサーを買って自分でつければ、かなり安く、しかも早く導入できる。
医療用じゃなくて、ゲームとか他の分野で進化してきたものも多いので、「使いたい」と思ったときに使えるのがいいですね。ただこれらは医療用のものではないので、トラブル発生時は自己責任で対応することになりますが(笑)。。
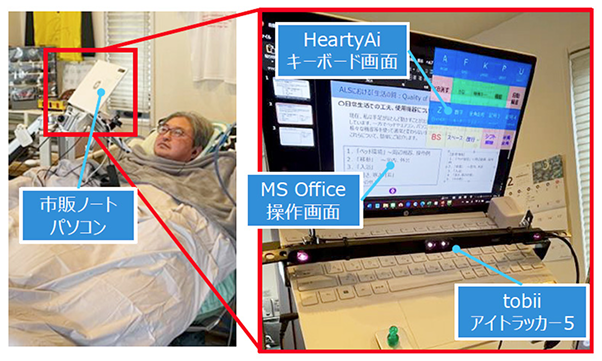
声が出せなくなったとしても、人工音声を使おうと思えば、今はもう使える時代なので。
そういったものをあらかじめ準備しておくことが大事だと思います。
今使えるものって、たとえばスマート家電とかアレクサとか、いろいろありますよね。
その中から、自分に合うものをチョイスしていく、っていう感じです。
ーどこかにまた不具合が生じても「乗り越えるっていう気持ち、何かをやろうっていう気持ち」が湧いてきますよね
柴田さん
そうですね。だんだん工夫してきて、今は玄関のドアのロックや解除もできるようになっています。
「こんなのが使えたら、あれもできそうだなー」って、いろいろ考えながらやってます。
SwitchBotのボットっていう、指で押すような動きをするロボットを使って、物理的なスイッチを押せるようにもしています。
それで、パソコンの電源も自分で入れられるようにしました。
ー柴田さんの家は未来のモデルルームみたいですね。ALS以外のいろんな方もこういう風に利用すればできるよって気持ちになりますね。
柴田さん
自分でできるところとできないところの線引き考えて、計画して生活していくうえでの工夫を考えますね。
それは私だけでなく、妻も作業療法士さんもいろいろアイデア出してくれます。
例えば、パソコンを動かすのに手元のボタンをカチカチと押すようになっているんだけど、そのボタンをどのように固定するのが良いかを妻や作業療法士さんが考えてくれています。
台を作ってもらって、そこに手を置くと大体の位置が決まりますよね。
台はわざと固定していなくて、軽く止めているだけで、これでいい感じに手が動くようになります。

ー工夫してみようって思えるかどうかって、大きいと思うんですよね。
なかなか前向きになれない方も多いと思うんですけど、少しずつ工夫を積み重ねていく中で、だんだん前向きな気持ちになっていけるのかなって。
柴田さん
自分が快適に過ごすために、「ちょっとでもこうなればいいな」っていうのは、やっぱりありますよね。
妻が見つけてくれたものの中に、水冷マットっていうのがあるんですが、寒いときでも、ずっと同じ位置に背中があると熱くなっちゃうんです。どうやってもダメで。
それで妻が通販番組を見て見つけてくれたんですが、水のパイプが通っている、ベッドに敷くシートです。普通の人が使っていいやつですね。
本来はリモコンで操作するんですけど、私はこれをアレクサで動かしてます。
「アレクサ、水冷マットオン」
→「水冷マットが起動しました」
病気のメンバーでつくってるメールグループがあって、そこでもこの水冷マット、おすすめしてます。
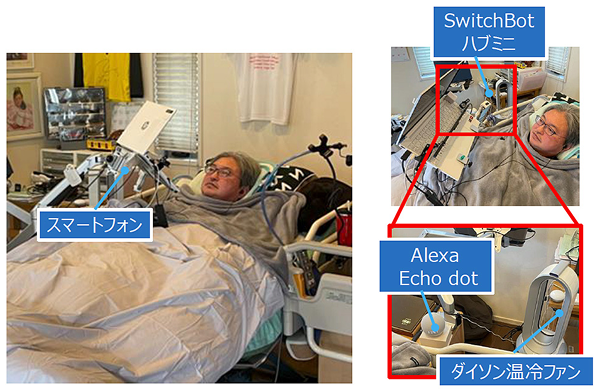
自分でできるっていうのも大きいよね(妻)
そうだよね、自分でできるのはすごく大きいです。人にお願いしないで自分できるのはすごく良いですよね。ある程度自分で動かせるっていうのはすごくモチベーションになりますよ
ね。ヘルパーさんに頼めばいいって言っても、やっぱり自分で出来る・出来ないっていのは全然違うので。
ー形態は変わったとしても今までの柴田さんの生活が続いているって感じですかね
柴田さん
体が動かなくても自分は自分だし、そこは同じですね。前から作るのも模型を作ったりものを揃えるのも好きだったし、今もそれが楽しみですし。
小学校の時からプラモデルが好きでした。飛行機とか世界の船とか好きでしたね。
車も好きだし、バイクも好きだし。バイクは1200のバイクを学生の頃から社会人になっても結婚した後も乗ってました。奥さんも了解済みで(笑)。
バイクに無線機つけて、そのスイッチをブレーキのところにつけて、ヘルメットにマイクとスピーカー仕込んで、先輩と一緒にツーリングしたりしてました。
ー自分の人生通して、今の病気とは別に、何か困難なことありましたか?
柴田さん
やっぱり、就職ですかね。転職したときに、企業文化の違いにはびっくりしました。
もともと大学院ではスポーツバイオメカニクスを専攻していて、卒業後はスポーツ用品の基礎研究に携わる仕事に就きました。
でも、その部門が縮小してしまいどうするか迷っていたところ、全く別の業界でしたが、それまで行っていたCAE解析の技術者を募集していた自動車メーカーに転職することにしました。
ただ、研究や開発の考え方やスタイルが、自分が思い描いていたものと違っていて。
仕事の進め方には戸惑いましたね。いろいろと新しいことも提案したんですが、時間がかかるものだし、なかなかうまくはいかなくて。
まったく未知の領域に取り組むことが多かったですし、完了するまでに10年くらいかかってしまったこともあるので、難しかったですね。
ー今の柴田さんにどうつながってますか?
柴田さん
結局、ものとしてできなかったとしても、「ここまでやりたい」っていう気持ちや、周りで見てる仲間や上司や同僚・部下の信頼ですよね。外から買ってくる技術じゃなくて、研究はゼロから生み出さないといけないから。そこを見てくれていたのはありますよね。
今は趣味みたいなものですからね。「産みの苦しみ」みたいなのはないって言ったらアレですけど……。
自分で考えたことを形にするとか、やってみて「あー、そうだな」って思うとか、そこの面白さは研究と一緒かもしれませんね。
今は手持ちのものを集めてきて、できるだけ労力を使わずにシステムを構築できるっていうのが理にかなってるから、やっています。
ー治療に一歩ずつ近づきながらも、日常の生活をより快適にするってことがご本人にとっても将来の薬を待つための一つの布石にもなると思いましたが
柴田さん
QOLはとても重要だと思っています。
今がしんどくてしんどくて、で、先を見るのはつらいことだと思います。
将来の薬は現実になるかはまだわからないので、それだけを頼りにするのは難しいと思います。
どんな手段でもいいから日常の生活を良くして、日常の生活のなかでも楽しみながらというか、少しでも快適に過ごせる環境は絶対に必要だと思います。
ー今ある技術を利用しながらということでしたが、もっとQOLを上げることが出来るとお考えですか
柴田さん
もうちょっと何かできるんじゃないかなって、やっぱり思いますよね。
たとえば、水を飲むっていう行動も、今はトレッキング用の飲み物入れを使って飲んでいますけど、これを簡単なマニピュレーターで、飲みたいときに飲めたらいいなって思ってます。
試してはいないけれど、フレキシブルなアームとかでできたらいいなというのはありますよね。
パソコンも視線で操作できるとはいえ、バグるときもあるので。
そういうときのために、緊急脱出用に動いてくれる“何か”があればいいな、と思いますね。
ー自分でできる自己決定がキーワードですよね
柴田さん
そこは非常に大きいですね。
ー今生活で前向きにされていることは奥さんはどう考えていると思いますか?
柴田さん
半分趣味だと思ってますよね(笑)
でも逆に、私がずっと病気のことばっかり考えてるよりは、いいんじゃないかなと。
子どもたちも、病気と関係なく、いつでも助けてくれますし。
妻にはたくさん負担をかけていると思うけど、少しでも快適になるようにって、いろんなクッションを見つけてきてくれたり、色々とやってくれてます。
やっぱり家族がいるってことで、気持ちも持ち直せますよね。
家族だけじゃなくて、日常に入ってくれてるヘルパーさんもそうだし、友人たちもたくさん来てくれます。
今日も、実は午前中に前の会社の同僚が遊びに来てくれました。
病気になったからって特別じゃなくて、普段どおりにできる。
「心配だから来る」じゃなくて、「ふらっと遊びに来てくれる」――そういう関係がありがたいですね。
妻もそういうのを嫌がらない、気さくな性格なので。
ー柴田さんの仕事をしていたときの前向きでチャレンジする精神性は病気になった後で変わりましたか?
柴田さん
前向きさは変わらない気がしますが、、子どもたちに言わせると丸くなったと言われます(笑)仕事してた時はピリピリしてたって言われます。子どもたちが大きくなったこともあると思いますが、、やはり仕事はどうしてもピリピリしちゃう(笑)
あと頼ったりできるようになったことも大きかったと思いますね。できないことはできないから頼るしかない。それが自然にできるようになったのかも。
ーALSをどういうふうに捉えれば、ALSの他の患者も柴田さんのように前向きに捉えられると思いますか
柴田さん
正直、むずかしいですね。ALSは進行のスピードや障害の出る場所が人によって全然違いますから。
僕は告知を受けて7年たってもまだ喋れていますが、人によっては1年たたずに話せなくなることもある。
そうなると、心の準備が追いつかないままに進んでしまう。もし自分がそういう立場だったら、今みたいにはいられないと思います。
コミュニケーションがとれるっていうのは、生活するうえで本当に大きなことです。
それが、声が出せなくなったときにどうなるか。心の準備ができていないままそうなるのは、すごくつらいことです。
それをどうフォローしていくか。本人が「使ってみよう」と思えるモチベーションにどうつなげていくか。
周りの助けも必要だし、本人ひとりだけではなかなか難しいと思います。
そこは本当に人それぞれなので、一人ひとりに合わせないといけないと思います。
最初にこの病気になって、宇都宮保健所で患者会があって、ご家族とお会いしました。ご本人がいらっしゃらず、ご家族だけの方もいました。その患者会で4、5家族と集まって話したときに、ALSは60〜70代が 発症なので、「あとはパチンコやってお酒飲めればいいや」みたいな考えの人もいました。何かやりたいこともないしっていう人もいたし。でも患者の中には若くて子どもが小さく て、どうしようっていう人もいる。それぞれ、どういうときに病気になったかも違うし、家族関係もうまくいってるかわからないし。月1回やってるZOOM座談会にもいろんな家族が 来るけど、参加してくれる人はどちらかというと前向きな人が多いですよね。出てこない人もたくさんいるし、患者会で呼びかけても来ない人もいる。そういう人たちに何ができるか って、本当に難しいですよね。「使ってみたら?」って言っても、使わない人は使わないし。
そういう会に参加していて、その会話の中に入っていかなくても、聞いているだけでも参考になることって、たくさんあると思います。
たとえば、「排便とかどうしてます?」とか、「おむつにできないから、こうしてる」とか、そういう患者同士の話を聞くだけでも、いいと思うんです。
発表とか、紙に書いてある文章とかではなくて、会話のキャッチボールを聞けるっていうのがあればいいなと思います。
自分が質問しなくてもいい状態で、勝手にやっている中で、「こういうものがあるんだ」って気付けるといいと思います。
それなら、ハードル低いかなと。
いろいろな情報がもらえて、いろんな考え方も知って、直接的な回答じゃなくても、参考になると思いますし。
ー柴田さんが今これはやってみたいなっていうことありますか?
柴田さん
そんな大それたことは考えてなくて。普段通りにできるだけ今の生活が維持できるように周りの環境と整えていきたいですね。機械にかぎらず、ヘルパーふくめ、レスパイト入院含め。
想定外のことっておきるじゃないですか。その時の備えがあるといいなと思います。そういった意味でいうとバッテリーを去年大きいの買いました。停電になったときにベットや扇
風機、水冷マットは動かせます。備えがあれば何かあったときに安心できるので、普段もあまり心配せずに過ごせます。
必要なものはその時その時変わっていきますよね。トイレできなくなったらポータブルトイレに移行するっていうことも考えています。自分の頭のなかや備えとしてあれば安心できま
すよね。日々の生活をしていくなかで、できるだけ穏やかにね、家族とね。3人の子どもは今年で下の子も就職してこれで全員就職しまして、東京に住んでます。LINE電話とかで話
しています。
スポーツや仕事やってて自分ひとりじゃどうにもならないことありますよね。同僚含め周りの理解含め信頼関係って大事ですよね。お願いしてやってもらったら感謝の言葉をつたえるのも大事だし。そういうのは大事で必要で、そういうのは変わらずですよね。
ー本日は、ALSというものを柴田さんがどう捉えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思っていました。
お話を伺って、病気にとらわれることなく、柴田さんが柴田さんとしてあるために、いろいろと準備をされてきたことがよくわかりました。
そのうえで、改めてお伺いしたいのですが、ALSというものを、どう捉えていらっしゃいますか?
柴田さん
ALSは避けようのない病気なので、どうしようもないですよね。
どうしようもないことは、自分が変わるしかない。そういう人生だと思って、生きていくしかない。
そういったなかでも、必要以上に悲観することなく。人間、いつ死ぬかわからないですからね。
事故や病気を含めて、いろんなことがあると思いますが、それは命あるもの全員に言えることなので。
そういったなかで、精一杯、自分の人生を生きればいいんじゃないかと思います。
自分ができる範囲のことを、やればいいのかなと。
いろんなことがあるのが人生なので。受け入れることをしないと、前に進めない。
「手放す」というより、「受け入れる」。これも自分の一部。
前はできたのにって思って、悲しい気持ちにもなりますけど、それって「若い頃はできた」とかと同じで。
できないものは、できない。
そこを考えるよりは、「今をどう生きるか」。病気に限らず、ですよね。
開く
![]()
・男性ヘルパーが少ない(私の体が大きいため、男性ヘルパー優先で入っていただいている)
・起床および就寝時と、土曜日半日および日曜日は家族(妻)が食事+トイレ+入浴介助をしてくれているが、妻の負担が大きい
・レスパイト入院先が少ない(二か所あるが常に空いているわけではない)
・発症前に私がしていた家周りの力仕事の人手が足りない(庭の手入れ、車や家の修繕など)
IoT機器の説明動画
IoT機器の説明資料
ALS協会栃木県支部のHP